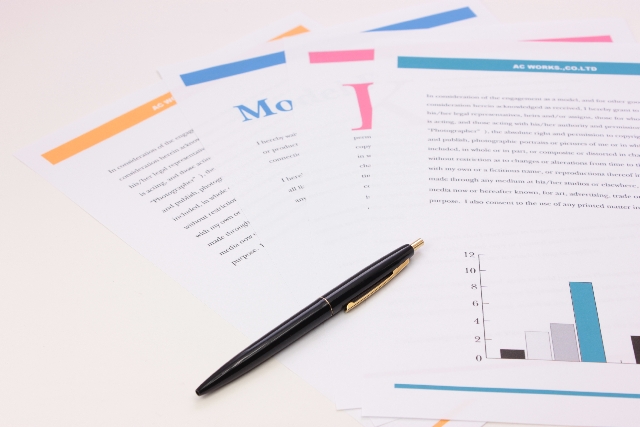


【健康保険どっちが得?】国保か期間限定で夫の任意継続保険の扶養に加入するべきか
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。
ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。
来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。
ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。
健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。
ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。
来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。
ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。
健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
国民健康保険は自治体管轄なのでいろいろ条件が異なります。
でも、任意継続の扶養対象になれるのなら保険料負担がない分が有利です。
節税とは別の話です。
国民健康保険を含む社会保険料を多く払う方が節税になります。
節税にならなくても出費が少ない方が得です。
でも、任意継続の扶養対象になれるのなら保険料負担がない分が有利です。
節税とは別の話です。
国民健康保険を含む社会保険料を多く払う方が節税になります。
節税にならなくても出費が少ない方が得です。
年金&保険料未納なのですが・・・
一昨年の暮れにやっとこ就職した会社を自主退社しました。
現在は請負派遣とアルバイトの掛け持ちでなんとか生活をしています。
月収は請負25万、アルバイト6万程度です。
私は22歳男性、未婚、一人暮らし(世帯主)です。
そろそろ確定申告が近づいてきたのですが、ふといろいろ不安になりました。
①前会社退職時に厚生年金から国民年金の変更手続きをしていない(未納状態12ヶ月間)
→差し押さえとかありそう・・・
②社会保険料を未納付(12ヶ月間)
→もし次に就職して、バレたらやばそう・・・
③確定申告がめんどくさい
→とりあえず、税務署に聞けば大丈夫かな?
④認定日にハローワークに行っていない
→失業保険をもらえないだけ?もしかしたら、今から行けば貰えるかな?
知識が無い私ではこれくらいしか困ることが考えられませんでした。
①~④で私がこれからすべきことや困ることを教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
一昨年の暮れにやっとこ就職した会社を自主退社しました。
現在は請負派遣とアルバイトの掛け持ちでなんとか生活をしています。
月収は請負25万、アルバイト6万程度です。
私は22歳男性、未婚、一人暮らし(世帯主)です。
そろそろ確定申告が近づいてきたのですが、ふといろいろ不安になりました。
①前会社退職時に厚生年金から国民年金の変更手続きをしていない(未納状態12ヶ月間)
→差し押さえとかありそう・・・
②社会保険料を未納付(12ヶ月間)
→もし次に就職して、バレたらやばそう・・・
③確定申告がめんどくさい
→とりあえず、税務署に聞けば大丈夫かな?
④認定日にハローワークに行っていない
→失業保険をもらえないだけ?もしかしたら、今から行けば貰えるかな?
知識が無い私ではこれくらいしか困ることが考えられませんでした。
①~④で私がこれからすべきことや困ることを教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
こんににちわ!!
大変だけど、確定申告は必要だよね
①②は、納めた方がいいですね
③は、退職金と請負(営業所得)、アルバイト(給与所得)で計算される為、
していかないと、国税の追徴、延滞金、重加算税等納める事になるからね
また、住民税も確定されないし、国民健康保険料もかかるしね
④は、どちらでもいいと思うね。今収入もあるからね
次の就職する時に、総務(給与)担当は直ぐに分るからね
大変だけど、確定申告は必要だよね
①②は、納めた方がいいですね
③は、退職金と請負(営業所得)、アルバイト(給与所得)で計算される為、
していかないと、国税の追徴、延滞金、重加算税等納める事になるからね
また、住民税も確定されないし、国民健康保険料もかかるしね
④は、どちらでもいいと思うね。今収入もあるからね
次の就職する時に、総務(給与)担当は直ぐに分るからね
教えて下さい。
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?
わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?
わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
↑概ね、こちらの方のおっしゃっているとおりですが、国民年金保険料は、13,580円/月です。
また、あなたがご主人の「被扶養者」となり得る条件は、過去の収入がいくらであったかでなく、「今後見込まれる収入」が130万円未満であれば「被扶養者」となり得ます。
また、あなたがご主人の「被扶養者」となり得る条件は、過去の収入がいくらであったかでなく、「今後見込まれる収入」が130万円未満であれば「被扶養者」となり得ます。
社会保険の扶養に入っていますが、年収には失業保険は関係あるのでしょうか?
失業保険の金額が加算されないなら扶養範囲の130万越えにはならないのですが 加算されると132万と少しオーバーしてしまいます
失業保険だけで42万あったので なければ 実際は90万くらいなのですが・・・
年収と所得とは同じ意味あいですか?
失業保険の金額が加算されないなら扶養範囲の130万越えにはならないのですが 加算されると132万と少しオーバーしてしまいます
失業保険だけで42万あったので なければ 実際は90万くらいなのですが・・・
年収と所得とは同じ意味あいですか?
本来「社会保険(健康保険)」の被扶養者であれば、当初より失業給付金を受給することはできません。
逆に申し上げれば、失業給付金を受給するのであれば、被扶養者の資格を喪失させておかなければならないということです。
失業給付金は「社会保険」に関しては「収入」と見なされます。
「年収」と「所得」はその性格が異なります。
↑ある一定の収入の場合「65万円」ですが、何でもかんでもではありません。
逆に申し上げれば、失業給付金を受給するのであれば、被扶養者の資格を喪失させておかなければならないということです。
失業給付金は「社会保険」に関しては「収入」と見なされます。
「年収」と「所得」はその性格が異なります。
↑ある一定の収入の場合「65万円」ですが、何でもかんでもではありません。
関連する情報